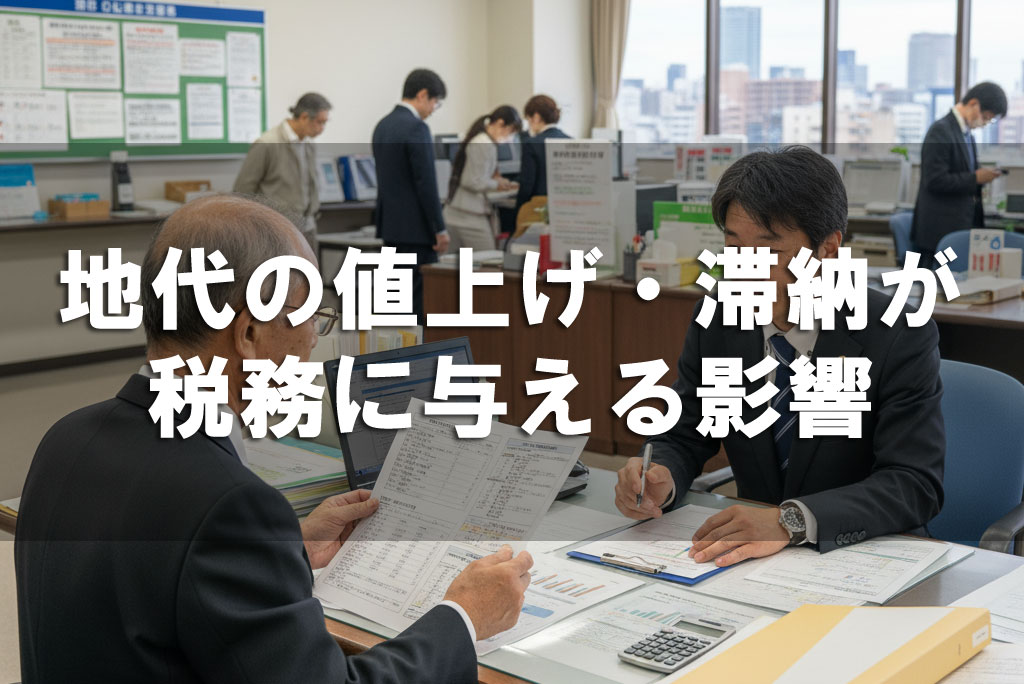
地代の値上げ(改定)や滞納は、底地オーナーの収入に直結するだけでなく、税務上も複雑な影響を及ぼします。
特に、税務署は地代の適正性や未収金の処理を厳しくチェックするため、適切な対応が必要です。
地代の値上げを怠った場合の「みなし贈与」
地代の値上げ(改定)を怠り、長期間にわたり周辺相場よりも著しく低い地代を維持していると、税務署から「相当の地代」との差額を借地権者への贈与とみなし、借地権者に贈与税を課税するリスクがあります。これが「みなし贈与」です。
【相当の地代の目安】
税務上の「相当の地代」の目安は、土地の更地評価額に対する年6%程度と言われています。
実際の地代がこれよりも低い場合、みなし贈与のリスクが高まります。オーナーに贈与の意図がなくても、税務署が客観的に判断するため、非常に危険な状態です。
【リスク回避策】
- 地代の適正水準への改定
地代を周辺相場に合わせて改定することが、最も確実なリスク回避策です。
改定が難しい場合は、不動産鑑定士に相談し、適正な地代水準に関する客観的な資料を準備しておくことが重要です。 - 適正な権利金等の受け取り
地代が低い状態が続く場合、代わりに借地権者から権利金や保証金といったまとまった金銭を受け取ること(この場合も課税関係が発生するため注意が必要)で、みなし贈与のリスクを軽減できる場合があります。
未収地代の扱いと「貸倒れ損失」
地代が滞納された場合、オーナーは実際に収入を得ていませんが、税務上の処理には注意が必要です。
- 原則:収入計上の義務(発生主義)
不動産所得の計算では、原則として未収地代も含めて収入として計上する必要があります。
つまり、入金されていなくても、本来受け取るべき地代は課税対象となり、所得税・住民税を支払う義務が生じます。 - 例外:貸倒れの処理
滞納地代が、借地権者の破産、死亡、または長期間の音信不通などによって法的に回収不能と確定した場合、その金額を「貸倒れ損失」として経費に計上し、課税対象から外すことができます。
【処法と証拠の重要性】
滞納が発生した場合、オーナーは以下の行動を徹底し、証拠を残しておくことが重要です。
みなし贈与リスクを避けるためにも、滞納発生時の処理を明確にするためにも、税理士との連携は不可欠です。
- 督促の記録
速やかに内容証明郵便などで督促を行い、回収に向けた努力の証拠を残す。 - 法的手続きの開始
回収が困難になった際は、税理士や弁護士と相談し、法的な手続き(契約解除、調停など)と並行して税務上の貸倒れ処理を検討する。
まとめ
地代の値上げを怠り、相場より著しく低い地代を維持すると、税務署から「みなし贈与」と指摘され、借地権者に贈与税が課税されるリスクがあります。これを回避するためには、「土地の無償返還の届出書」の提出や、適正な権利金・保証金の受け取りを検討することが重要です。
また、地代が滞納した場合でも、原則として未収地代は収入として課税対象となります。回収不能が確定した場合は「貸倒れ損失」として経費計上が可能ですが、必ず督促記録などの証拠を保全し、税理士と連携して法的な手続きを進める必要があります。税務上のリスクを避けるため、地代の適正化と交渉記録の保全を徹底しましょう。
