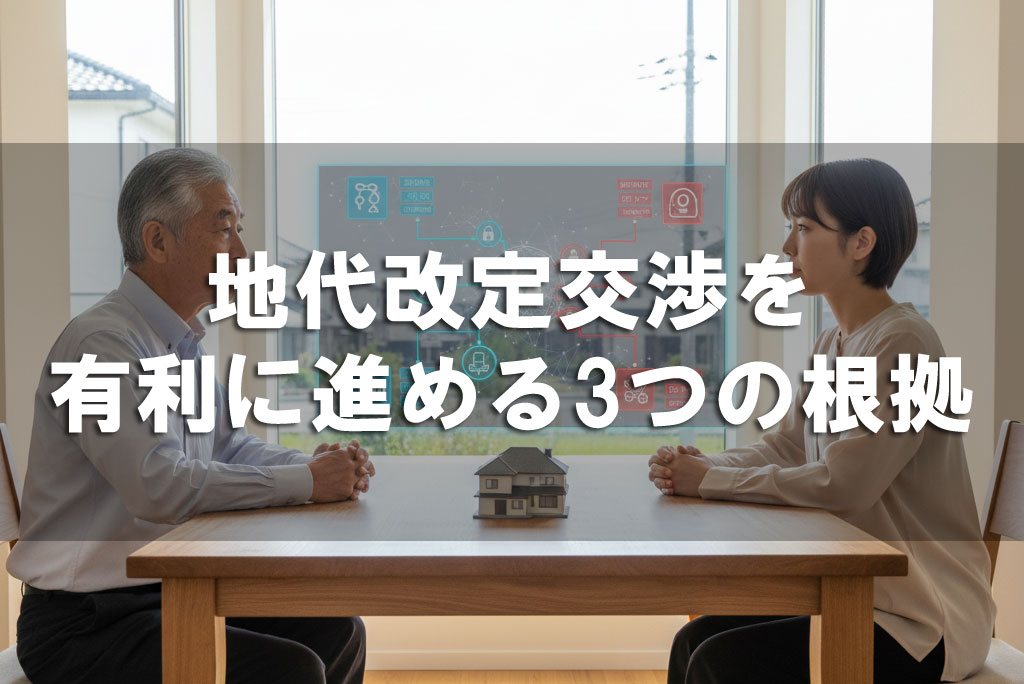
底地オーナーにとって、地代改定交渉は底地経営の収益性を左右する最も重要な交渉です。長期間にわたって地代を据え置くと、固定資産税・都市計画税(公租公課)の合計額が地代収入を上回る逆ザヤ(赤字)状態に陥るリスクが高まります。借地権者は地代の値上げに消極的ですが、オーナーが法的に正当な根拠を提示することで、交渉を有利に進めることが可能です。地代改定交渉を成功させるための具体的な根拠と手順を理解しましょう。
地代改定交渉の法的根拠:借地借家法第11条
地代の改定は、借地借家法第11条によって認められています。同条は「土地に対する租税その他の公課の増減」や「土地の価格の上昇又は低下その他の経済事情の変動」により、地代が不相当となった場合には、当事者は地代の増減を請求できると定めています。オーナーは、この条文に裏付けられた以下の3つの客観的な根拠を提示することが重要です。
交渉を有利に進める3つの客観的根拠
地代の改定は、借地借家法第11条によって認められています。同条は「土地に対する租税その他の公課の増減」や「土地の価格の上昇又は低下その他の経済事情の変動」により、地代が不相当となった場合には、当事者は地代の増減を請求できると定めています。オーナーは、この条文に裏付けられた以下の3つの客観的な根拠を提示することが重要です。
1.公租公課の増額
これは最も説得力があり、客観的な根拠です。固定資産税・都市計画税(公租公課)の合計額が上昇している事実を示し、「公租公課を下回る地代では、底地経営が赤字になる」という経済的な理由を提示します。
- 提示資料
過去数年分の固定資産税・都市計画税の納税通知書のコピー(オーナー控え部分)。 - 交渉術
最低でも地代が公租公課の3~5倍程度になる水準を目標として提示します。
2.近隣類似の地代相場との比較
周辺の類似した条件の底地の地代水準が、自身の底地よりも高いことを示し、「経済事情の変動により不相当となった」ことを立証します。
- 提示資料
近隣の不動産鑑定士による地代の鑑定評価書、または不動産業者からの相場調査報告書。 - 注意点
この根拠は客観的な資料が必要であり、単なる「近所の人に聞いた話」では通用しません。
3.土地価格の上昇(経済事情の変動)
周辺の類似した条件の底地の地代水準が、自身の底地よりも高いことを示し、「経済事情の変動により不相当となった」ことを立証します。
- 提示資料
過去数年間の路線価図や地価公示価格の推移を示す資料。 - 交渉術
「みなし贈与」のリスク(地代が安すぎると借地権者に贈与税が課されるリスク)を指摘し、値上げが借地権者にとっても利益になる可能性を間接的に示唆します。
交渉の手順と調停・訴訟への移行
- 事前準備
上記3つの根拠となる資料を全て収集し、希望する改定後の地代を算定します。 - 交渉開始:借地権者に対し、地代改定の理由と根拠、希望額を記載した書面を送り、話し合いの場を設けます。口頭だけでなく、記録を残すことが重要です。
- 調停申立て:話し合いが不調に終わった場合、オーナーは裁判所に地代増額の調停を申し立てる必要があります。調停前置主義により、原則として訴訟の前に調停を経なければなりません。
- 訴訟:調停でも合意に至らなかった場合、地代増額請求訴訟を提起します。この段階では、裁判所が選任した不動産鑑定士による鑑定評価が最も重要な証拠となります。
地代改定交渉は感情的になりがちですが、オーナーは一貫して客観的なデータに基づいた冷静な姿勢を保ち、借地借家法に強い弁護士と連携して手続きを進めることが、成功への鍵となります。
