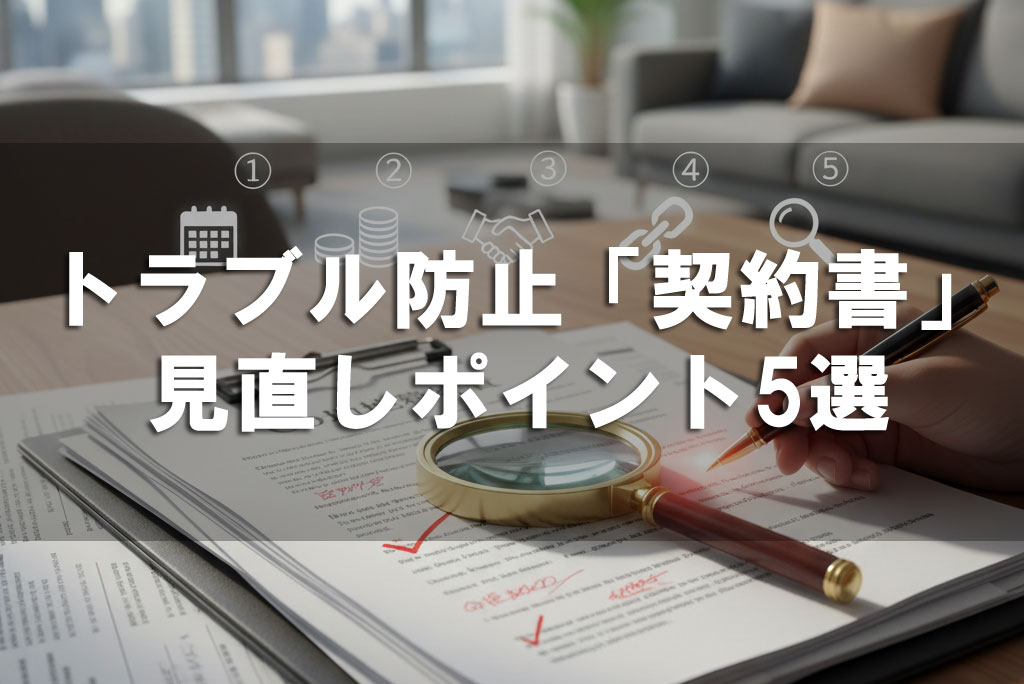
底地トラブルの多くは、実は契約書の内容があいまいなまま放置されていることが原因です。
借地契約は長期にわたるため、契約時の法律や慣習が現在と異なっているケースも少なくありません。
「昔からの付き合いだから大丈夫」と安心していると、更新や相続のタイミングで思わぬトラブルになることも。
ここでは、底地オーナーがチェックしておくべき契約書見直しの5つのポイントを紹介します。
契約期間と更新条件
契約期間が「旧借地法」時代のままになっていませんか?
旧法では借地権の期間が初回30年、以後20年ごとに更新とされていますが、新借地借家法では普通借地契約(30年)または定期借地契約(50年など)といった形が主流です。契約更新の際には、「自動更新」か「合意更新」かを明確にし、終了条件や更新料の有無を文書で定めておくことが重要です。
地代の金額と改定方法
地代はトラブルになりやすい項目です。
特に「相場変動に応じた改定方法」が明記されていない場合、長期間にわたり不公平な状態が続くことがあります。
地代の見直しについては、下記項目を契約書に具体的に記載しておくと安心です。
- 改定時期(例:3年ごと)
- 改定理由(例:地価変動・経済状況)
- 交渉手順(例:書面通知→協議)
承諾が必要な行為の範囲
借地人が建物を建替え・譲渡・転貸する際には、オーナーの承諾が必要です。
しかし、古い契約書ではその範囲が曖昧なことが多く「これは承諾が必要なのか?」という点でトラブルが発生します。
建替え・改築・用途変更など、どの行為に承諾が必要かを明記し、必要に応じて承諾料の算定基準も設定しておくと良いでしょう。
契約違反時の対応・解除条件
契約違反が発生しても、契約書に明確な「解除条項」がなければ対応が難しくなります。
例えば、地代の滞納や無断転貸などがあった場合に、下記について具体的に記載しておくことでトラブル発生時に法的根拠を持って行動できます。
地代の見直しについては、下記項目を契約書に具体的に記載しておくと安心です。
- 何回の催告で解除できるか
- 違反時の損害賠償や遅延利息の扱い
契約書の保管と共有方法
契約書が紛失していたり、写ししか残っていないケースも珍しくありません。
複数人で底地を相続している場合は、全員が契約内容を把握できる仕組みを整えておくことが大切です。
原本の保管はもちろん、デジタルコピーを作成し、相続人間で共有しておきましょう。
まとめ
借地契約書は、底地運営の「ルールブック」です。
古い契約のまま放置しておくと、借地人との認識ズレがトラブルの火種になります。
定期的に契約書を見直し、現行法や実勢に合った内容にアップデートしておくことで、安心・安定した底地運営を続けることができます。
