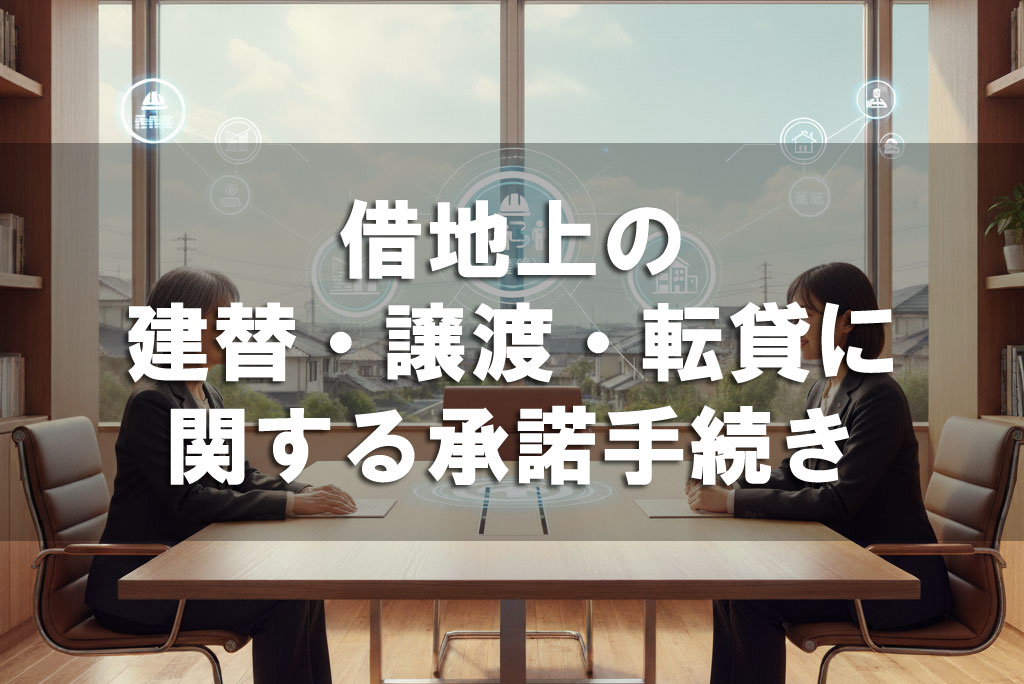
底地を所有していると、借地人から「建物を建て替えたい」「第三者に譲りたい」「一部を転貸したい」といった相談を受けることがあります。
こうした行為には、原則として底地オーナーの承諾が必要となります。
しかし、承諾をめぐるトラブルは少なくなく、承諾料の妥当性や条件交渉で揉めることもしばしば。
本コラムでは、借地における承諾手続きの実務的なポイントと注意点をわかりやすく解説します。
承諾が必要となる主なケース
借地契約においてオーナーの承諾が必要とされる行為は、主に以下の3つです。
これらはいずれも土地の利用形態や契約関係に直接影響を与えるため、オーナーの判断が求められます。
信託(底地の運用可能資産化)の主なメリットは次の通り。
- 建替承諾:老朽化した建物を新築・改築する場合
- 譲渡承諾:借地権を他者に譲渡する場合(相続は除く)
- 転貸承諾:第三者に土地を貸す場合
承諾を拒否できるケースとできないケース
オーナーは無条件で承諾を拒否できるわけではありません。
裁判所は、合理的な理由がない拒否を「権利の濫用」として認めない傾向にあります。
例えば、建物が老朽化しており、安全性の確保のために建替えが必要な場合などは、正当な理由なく拒否するのは難しいとされています。
ただし、借地人が契約違反を繰り返している、地代滞納があるなど、信頼関係が破壊されている場合は、拒否が認められる可能性があります。
承諾料の考え方
承諾料は法律で定められているものではなく、慣習や個別交渉によって決まります。
目安としては以下のような水準が一般的です。
- 建替承諾料:底地価格の3〜5%程度
- 譲渡承諾料:借地権価格の10%前後
- 転貸承諾料:借地権価格の3〜5%程度
ただし、これらはあくまで参考値であり、地域の商慣習や契約内容によって大きく異なります。
鑑定士による評価をもとに金額を算定すると、トラブルを避けやすくなります。
書面で承諾を残すことの重要性
口頭で承諾を行うと、後日「言った・言わない」の争いに発展する可能性があります。
必ず書面(承諾書)で合意内容を明記し、承諾料の金額、支払い時期、承諾の範囲を明確にしておくことが大切です。
特に建替承諾の場合は、建物の用途変更や増改築の可否なども併せて記載しておくと安心です。
承諾に代わる裁判手続きもある
もしオーナーが承諾を拒否した場合でも、借地人は裁判所に「承諾に代わる許可」を申し立てることができます(借地借家法第17条など)。
裁判所が適正と判断すれば、オーナーの承諾がなくても建替や譲渡が認められることもあります。
このため、感情的な拒否や高額な承諾料の請求は避けることが、円満な契約関係を維持するうえで重要です。
オーナーとしての適切な対応策
承諾を求められた際には、下記の3ステップを踏むことで、将来的な紛争を未然に防ぐことができます。
- 契約書を確認し、承諾条項や特約の有無を把握
- 専門家(弁護士・不動産鑑定士)に相談して相場を確認
- 書面で明確な合意を交わす
まとめ
借地上の建替・譲渡・転貸に関する承諾は、底地オーナーにとって重要な判断の場面です。
感情的に対応せず、法律や慣習を踏まえて冷静に判断することで、長期的な安定経営と借地人との良好な関係が築けます。
「承諾」は単なる形式ではなく、リスクマネジメントの一環として位置づけましょう。
